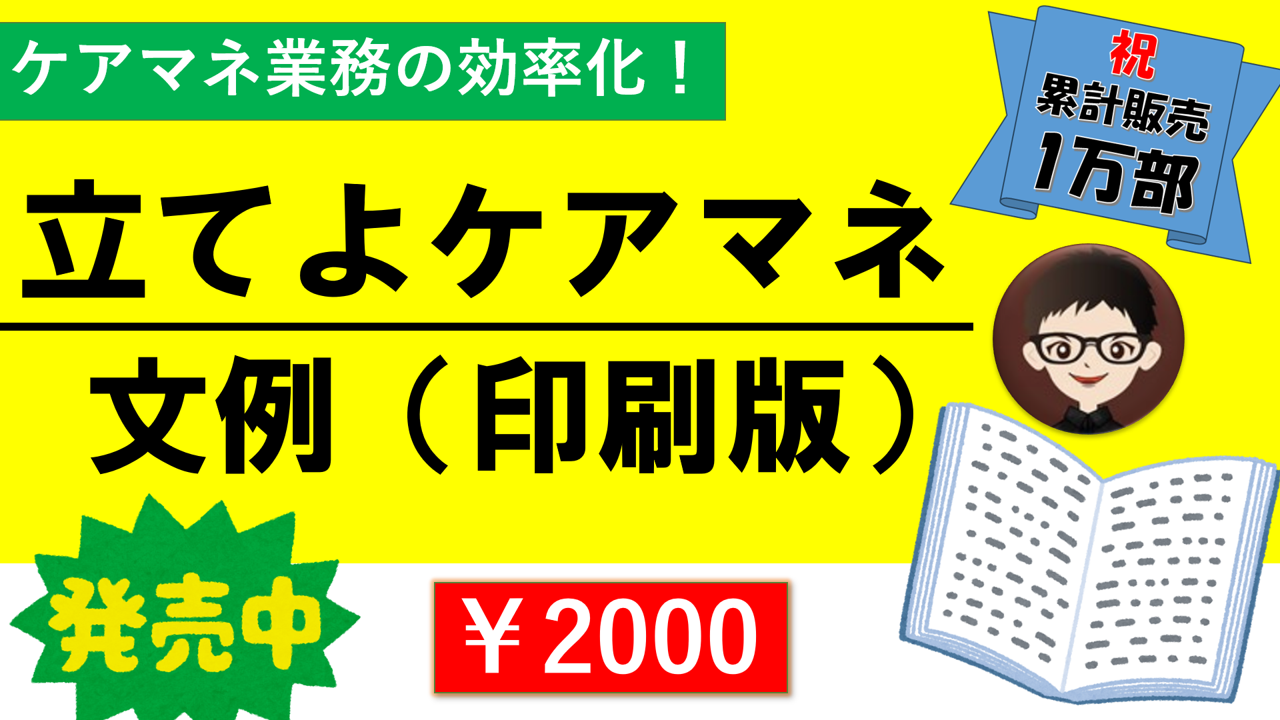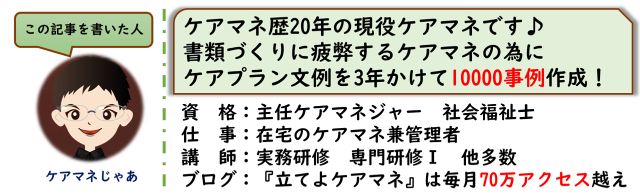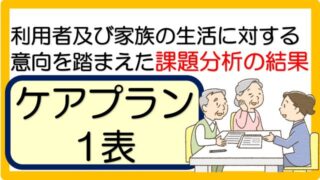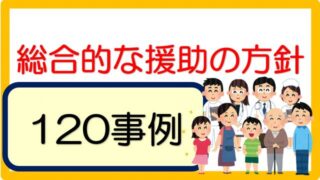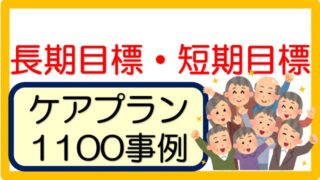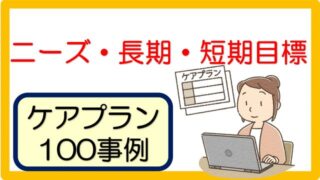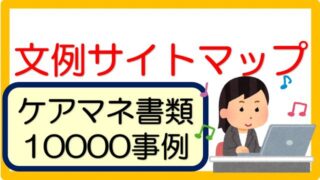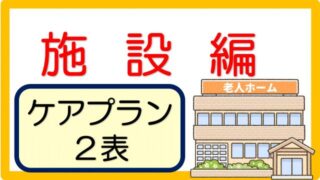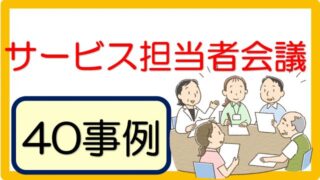はじめてケアマネに電話する
はじめてケアマネと面談する
そんな時利用者や家族はどんな気持ちだろうか?
想像してみてほしい
人は、まず悩みが生じたとき どうするだろう?
まず、自分自身で解決しようと試みる
例えば健康診断の検査数値が悪かった場合
まずは食事療法や運動療法を試みる
本屋やネットで情報を収集し
自分の力で何とか解決しようと試みる
それでも解決できない場合
家族や友人・知人などに相談してみる
それでもなお解決できない場合に専門家(プロ)に相談するのだ
この場合、病院などの医師になるだろう
つまり、ケアマネ(介護支援専門員)のところに相談に来るには
これまでのようなステップを踏んで
止むに止まれず
藁にもすがる思いで相談に来ていることを想像しなくてはならない
出来ることならケアマネの力など借りたくなかったはずだ
ケアマネは介護の専門家(プロ)として
最後の頼み綱なのだ!
そうなると当然
『あ〜ケアマネに相談してもだめだったか・・・』
では何のためにケアマネは存在しているのかわからない
我々はプロとしてその期待に応える必要がある
合言葉は
『話してよかったケアマネジャー』
『利用者の困ったをよかったに!』
| コピペで使える支援経過記録 文例集 |
|---|
| 初回面談 |
| 【初回電話相談】 利用者の長女より電話あり。一人暮らしの母の介護のことで悩んでいるとのこと。電話では長女の悩み、主訴を聞くことに専念し、詳しい内容は後日自宅に訪問し面談にて確認することにした。〇月〇日に自宅に訪問することにする ※詳細はアセスメントシート参照 |
| 【初回面談実施】 利用者宅を訪問し、介護支援専門員証の提示を行い、自己紹介をした後にインテーク面接およびアセスメントを実施する。利用者の主訴及び家族の希望、身体状況や介護力、生活環境等についてアセスメントを実施する。 (アセスメントを実施することについてその趣旨を説明し、同意を得る)※別紙参照 |
| 【病院での面談実施】 〇〇病院の病室を訪問し、介護支援専門員証の提示を行い、自己紹介をした後にインテーク面接およびアセスメントを実施する。利用者の主訴及び家族の希望、身体状況や介護力、病状、生活環境等についてアセスメントを実施する。 (アセスメントを実施することについてその趣旨を説明し、同意を得る)※別紙参照 |
| 【病院での情報収集実施】 〇〇氏の担当ケアマネジャーである事を伝えたうえで、〇〇病院の病院スタッフ〇〇氏より医療情報を聴取する。病状、退院の見込み、リハビリ計画、退院前カンファレンスの日程などの確認を行う。 ※詳細は別紙参照 |
| 【介護保険者被保険者証の確認】 利用者および家族の同意を得て、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認する。 |
| 【身分証の携行】 利用者および家族に対して介護支援専門員証を提示し、今後担当介護支援専門員としてケアマネジメントを実施していくことについて同意をもらう。 |
| 契約時 |
|---|
| 【契約について】 サービス利用開始にあたり、契約書および重要事項説明書等について利用者本人及び家族に説明し、同意・捺印を頂き交付する。合わせて入院した際には、担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該医療機関に伝えるよう、利用者又はその家族にお願いし同意を得た。 ※担当ケアマネジャーの連絡先を記入したカードを介護保険証ケースまたはお薬手帳のなかに入れてもらうようお願いする。 |
| 【複数の事業所選択と選定理由】 利用者及び家族に対し、当該地区における指定居宅サービス事業者等の名簿、サービスの内容、利用料等の情報を提供し、複数の指定居宅サービス事業者等の中から、利用者又はその家族がサービスの選択を可能であることをとを説明した後、サービス事業所の選定理由について介護支援専門員に対して求めることが可能であることを説明する |
| 【個人情報の同意】 利用者及び家族等の個人情報の取り扱いについて、その利用目的、第三者への提供等の説明をした後、文書により同意を得た。 |
| 【金品収受の禁止】 介護保険法において、利用者や家族等からのケアマネジャーに対する金品(心付け・進物)の収受は固く禁止されていることについて説明し理解を求める。 |